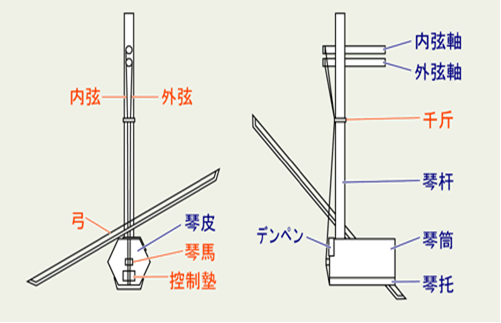新着情報
台湾二胡(ニコ)奏者ウェイ・リーリンのオフィシャルサイトへようこそ。
~台湾と日本を中心に世界の音楽・楽器の融合という独自の世界をめざしています~
4000年の歴史を持つ伝統楽器の二胡。 哀愁をおびた心揺さぶる音色は、悠久の世界を表現します、ピアノ・キーボード伴奏を加え、台湾と西洋の融合をめざします。 多様なアレンジを施し、台湾の曲、クラシック、ポピュラー、日本の曲からお子様向けの曲までレパートリーが広がります。
小学六年生の時、学校で偶然に二胡の演奏を聴く機会があり、人の心を動かす素晴らしい音色にすっかり引き付けられてしまいました。そして「二胡を上手に弾けるようになって、ステージで演奏するんだ」と自分自身に誓いました。その時は、放課後飛ぶようにして家に戻り、両親に「二胡を習わせてほしい」と頼みました。こうして私と二胡の縁が結ばれたのです。私に二胡を習わせてくれた天国の父母の恩に感謝していますし、現在、国を越えて二胡音楽と文化のプロモーション活動をする機会があるのも、父母のおかげと感謝しています。
1972年、志望していた国立芸術専科学校に入学し、立派な先生方から行き届いた指導を受けることができました。私が師事した董榕森、陳裕剛、林昱庭の三人の先生はいずれも中国伝統音楽と二胡の優れた演奏家を育てていらっしゃいます。在学中は二胡への熱い思いがますます募り、絶えず勤勉に練習を重ねました。卒業後は音楽教室を開設し、指導の現場に立つことで自らも学ぶことができました。高等中学、高等職業学校、専科大学などの国楽アンサンブルで指導にも当たりました。
日本に来てからは二胡演奏家として、日本各地のステージで活動するほか、吹田と堺市で【日台文化芸術院】「旧中華芸術院」を創立し、華僑のチャリティー活動に参加し、また、老人ホーム、病院、学校などに生徒さんを引率して慰問演奏するためのボランティア団体も設立しました。時間のある時は、遊びがてら豪華客船で船客のための演奏などもしますが、これも面白い経験です。また、毎年生徒さんや愛好家の皆さんと一緒に観光も兼ねて訪台し、国楽協会の行う検定テストに参加しています。
近年は、各界華僑団体の皆さんから推薦していただいて、大阪中華学校の国楽演奏グループの指導も担当しています。このように華僑と日本人の子弟を指導し、海外での中華文化の芽を育てる機会が得られて、より一層、「中華文化を伝承し、振興させなくては」と使命感を抱くようになりました。今もその活動を続けようという信念と熱意は私の心を満たしています。これからも日本で中華文化の振興と若い芽を育てるために、心と力を尽くすことができれば、本当に嬉しく思います。
台湾ツアーに参加した門下生の声から
・検定では偉い先生方が真剣に採点してくださり、丁寧で心のこもったコメントをたくさんいただいた。こんなことは一般人の私にとっては夢のようなことで、次はもっと練習を頑張らなくては、と思った。
・演奏会にはあふれるほどの人々が来て下さった。しかも誰もが熱心に聞き、心から喜んでおられるのはステージの上からもよくわかった。最後の「阿里山」では会場全員が一体となり、音楽には国境も言葉の違いもない、と大きな感動であった。
・演奏会の当日まで老師がしてくださった現地との打ち合わせや、いろいろの準備事に感謝感謝です。検定だけでなく、現地の方たちとの触れあいの機会を経験できることが、老師のツアーの素敵なところです。
・嘉義市での野外コンサートはたくさんの人が最後まで楽しんでくださった!浴衣がウケたこと!二胡検定に合格できたこと!台湾の新幹線に乗れ、観光も、たくさん買い物もできたこと!二胡を通して貴重な体験がたくさんできたこと!多くの人の親切に支えられてよい旅ができました!
・今回の台湾検定ツアーはとても勉強になり、みなさんとも同じ仲間という意識が芽生えました。
最後に
魏さんは人懐こくて、世話好きのお母さんのようだ。「先生は優しさと母性溢れる演奏をなさいます。レッスンも笑顔溢れ、いつも楽しい先生です!」と生徒に評される通りである。思いやりに溢れる彼女は、公益的な活動に参加を求められたら、力の限り頑張ってそれに応えようとする、そして使命感をもって、日本と台湾の文化交流に熱心に取り組んでいる。魏さんならきっとこれからも、より広く愛好者や演奏家、生徒達を率いて、文化交流の夢の実現のために努力し続けてくれるだろう。

楽器の紹介
二胡(にこ)というのは、日本でいわゆる「胡弓」と呼ばれている楽器です。 アジアには「胡弓」という楽器は存在しません。「胡弓」というのは日本語であり、日本で生まれ育ったある伝統的な和楽器の名称です。 「胡弓」と「二胡」は、まったく違う楽器です。「二胡」は中華の伝統的擦弦楽器です。 日本語では「にこ」、漢語では「erhu あるふー」と読みます。高胡や京胡など二胡と同じような構造の楽器がアジアにはたくさんあり、これらを総称して「胡琴(huqinふーちん)」と言います。 (「胡弓」は日本の楽器。弦が3本あり形も音色も奏法も成り立ちも大きく違う、まったく別系統のもの。)
二胡は20世紀に入ってから独奏楽器として改良され、アジアの胡琴の中でもっともポピュラーな楽器になりました。ちょうど西洋楽器におけるヴァイオリンのようなポジションです。 音色も大変ヴァイオリンに似ています。ヴァイオリンだと思って聞いていた音色が実は二胡だった。最近の二胡ブームを反映してか、CMやドラマの挿入曲で頻繁に耳にするようになりましたね。